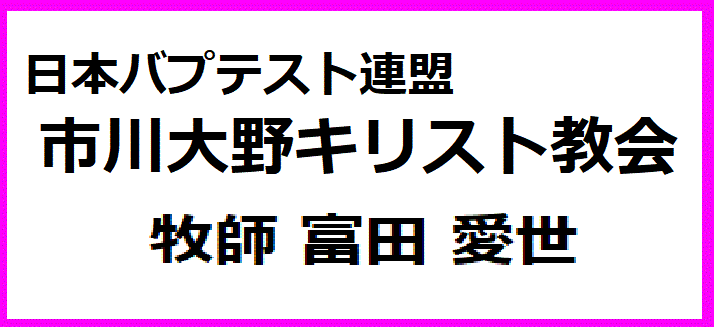前 奏 招 詞 詩編24編1節 讃 美 新生 5 神の子たちよ主に帰せよ 開会の祈り 讃 美 新生290 主の祈り 主の祈り 讃 美 新生602 まもなくかなたの 聖 書 マルコによる福音書10章29~31節 (新共同訳聖書 新約P82)
「神の家族」 マルコによる福音書10章29~31節
宣教者:富田愛世牧師
【召天とは】
今日の礼拝は「召天者を覚える日」の礼拝です。長く教会に来ている人にとっては、この言葉は違和感なく受け入れられるのかも知れませんが、実際には、この召天という言葉はあまり聞きなれない言葉だと思います。ワープロで「しょうてん」という文字を変換すると「昇天」天に昇るという文字に変換されるのです。つまり、教会で用いている「召天」という言葉は、一般的に使われる言葉ではない、という事なのです。
召天とは読んで字のごとく「天に召される」事です。一般的な概念では、天というのは空の上の方にあるどこかを意味します。ですから一般的な意味で使う場合は、しょうてんと言うと「昇る」という字を使った「昇天」になるのが当然です。しかし、聖書に書かれている「天」とは物理的な空間を意味する言葉ではなく、神の領域を意味する言葉なのです。ですから一般的ではないかもしれませんが、わざわざ「召天」と書くのです。そして、召されるとは、国語辞典によるならば、目上の者によって招かれる事を意味します。つまり、教会で用いる「召天」とは、この世での生涯を全うし、神のもとに招かれる事を意味するのです。
神のもとに招かれると言うと、とてもきれいな言い方ですが、実際には死を意味しています。死というのは人類共通の敵のようなものです。太古の昔から人類は死と向き合い、死と戦ってきましたが、死に勝つことは出来ませんでした。必ず人は死んでいったのです。そして、死に結びつくような病気や戦争を嫌ってきたのです。死によって、すべてが終わってしまい、無になってしまうと考えていたのです。
しかし、聖書の語る「死」とは、すべての終わりや、無になる事ではありません。肉体としての体は滅びてしまうかもしれませんが、人間の本質的な部分、つまり魂は滅びてしまうのではなく、天において永遠の命に与るというのです。聖書の語る肉体的な死とは、新しい命の始まりを意味しているのです。
【召天者記念礼拝】
キリスト教はよく「死者に冷たい」と言われます。特に日本のプロテスタントの教会にこの言葉は当てはまるようですが、この批判をそのまま返すとどうなるでしょうか。一般的な日本人は死者に冷たくないのでしょうか。そう言うと決まって「きちんと供養をしています」という答えが返ってきます。しかし、本来、供養とは仏や菩薩に真心から供物を供える事で、死者のためとは言えないものなのです。
日本の仏教は日本古来の風習の影響を強く受けています。日本の風習では死とは穢れでした。この穢れという概念は、何かわけの分からないものに対する恐れから出てきた概念で、それこそ不条理な概念です。神道では、そのような恐ろしい死者が自分たちに悪さをしないようにという事で、死者を神として祀るようになりました。死者に冷たいどころか、死者に失礼な態度から出てきた事なのです。仏教が日本に入って来た時に、そういった死に対する穢れの概念の影響を受けて「死者の供養」をするようになりました。もともとの仏教では、死というのは涅槃に入る事なので、恐れでもなんでもなかった、かえって喜ばしい事でもあったのです。
私は仏教をかじった者として、仏教は非常に素晴らしい教えだと思っています。しかし、それが日本の風習に取り込まれる中で変質してしまい、よく批判の対象となる「葬式仏教」的なものになってしまった事がとても残念だと思うのです。死者を供養するという行為には、死者に対する恐れの概念があります。供養しなければ、極楽浄土に行く事が出来ない。成仏できない。成仏できなければ、この世に対する未練から、化けて出てくるというような、きわめて死者に対して失礼な感情があるのです。
しかし、教会で行う召天者記念礼拝は「供養」ではなく、愛する者を失った遺族に対する慰めと励ましのために行っています。死によって分かたれてしまい、この地上においては愛する者ともう二度と会う事は出来ないのです。会う事が出来ないし、どこに行ったのかもよく分からない、それゆえに様々な心配が起こりますし、寂しい思いをするのです。これはごく当たり前な人間としての感情なのです。けれど、聖書は心配する事はないと宣言するのです。なぜなら、神によって、神のもとに呼ばれたのだから安心していいのです。
【すべてを捨てる】
さて、今日の聖書に目を向けて見たいと思うのですが、この箇所における一つのテーマは家族という事です、家族というのは、お互いを思いやる最小の単位です。ユダヤや日本では、家族を考える時に血のつながりという事を大切にしますが、私にとっては非常にナンセンスな感覚に思えるのです。なぜならば、家族の最小の単位は夫婦だと思うからです。この関係には血のつながりはありません。あってはいけない事になっているのです。聖書でははっきりとアダムとエバの出来事が書かれ、そのずっと後の時代になってから血のつながりが語られるのです。つまり関係性が一番大切だという事が暗黙の了解になっているのではないかと思うのです。
そして、血縁ではなく、愛に根ざした家族という関係が大切だと語るのですが、イエスはこの聖書の中で「家、兄弟、姉妹、母、父、子、もしくは畑を捨てた者は」と語ります。なぜイエスはこんな事を語るのでしょうか。家族という関係を否定しているのでしょうか。そんな事はないのです。実はここでイエスが語るのは「家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑」となっています。肝心なものが抜けていることに気付きませんか。「夫と妻」が抜けているのです。という事は、家族の最小単位である夫婦の関係があれば、いくらでも修復が可能だと言っているのではないかと思うのです。
また、イエスの言葉はとても冷たい言葉に聞こえますが、イエスは決してきれいごとを言わないという事がここから分かるのです。すべての人は「家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑」を捨てたくないと思っても、捨てなければならない時が来ます。それは「死」を迎えた時です。順番から行けば「母と父」については捨てるというより、捨てられてしまう形になりますが、「家、兄弟、姉妹、子、畑」に関して言えば、自分が死ぬ時、一緒に持っていくことは出来ません。この世に捨てて行かなければならないのです。
これらは大切なものですが、永遠に続くものではなく、一時的なものなのです。一時的なものに、大きな価値観を置くことは、とても愚かな事です。本当に価値のあるものを見つける必要があるのです。
【捨てることによって得る】
商売では「損して得とれ」という事が言われます。目先の利益にとらわれるのではなく、長期的な視野でものを見るという意味です。これは商売だけに限ったことではなく、今日の聖句にもつながるものです。というより、歴史的な流れから言うと、このような聖句が、様々な時代や文化、環境の中で適用されながら派生していって、行き着いた一つの先が浪速商人の心意気だったと言ったほうが正確かもしれません。
何事においても、私たちは大きな流れという事に注意しておかなければなりません。大きな流れの中に、様々な小さな流れがあり、いろんな事柄が起こるのです。小さな流れには逆らう事が出来ても、大きな流れに逆らう事は、非常に難しい事なのだと思います。
私たちの人生、生涯という事を考える時、この地上における百年くらいの長さで考えてはいけないのです。聖書が語る永遠という大きな流れの中で考えていく必要があるのです。
永遠という大きな時の流れの中で考える時、今を生きるための価値観に留まっていてはいけない事に気付くはずです。イエスが語る新しい価値観は「先の者はあとになり、あとの者は先になる」という福音なのです。不公平な言葉に聞こえるかもしれません。しかし、それは私たちが効率主義という現代社会の価値観に埋没しているからです。効率主義は弱肉強食という基本原理の上にしか成り立ちません。そこでは小さい者や弱い者はどんどん切り捨てられるのです。
神は私たちを神の子として招いてくださいます。神の家族の一員として迎えようとしているのです。その思いに答えたいとは思いませんか。その思いに答えるという事は、何かをする事ではありません。聖書によるならば、ただ信じることなのです。人間の親子でさえ、子が親を信じる時、親は必ず子にとって最善の事をなそうとします。ましてや神がそれ以上の事をされないはずがありません。私たちは神の最高傑作として、永遠の命を受け継ぐ者として創造されたのです。
讃 美 新生576 共に集い 主の晩餐 献 金 頌 栄 新生668 みさかえあれ 祝 祷 後 奏