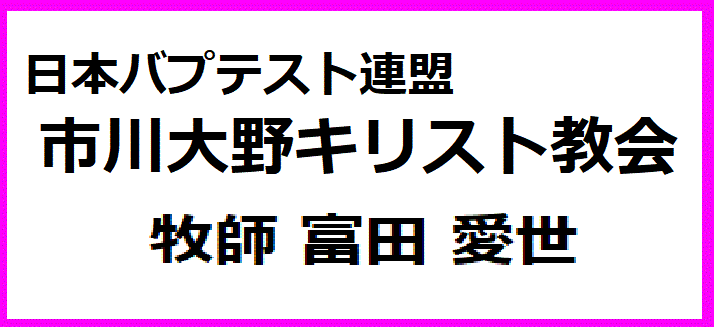前 奏 招 詞 詩編29編2節 讃 美 新生 20 天地治める主をほめよ 開会の祈り 讃 美 新生120 主をたたえよ 力みつる主を 主の祈り 讃 美 新生278 主イエスこそわが命 聖 書 マルコによる福音書12章35~44節 (新共同訳聖書 新約P87)
「神に愛される人」 マルコによる福音書12章35~44節
宣教者:富田愛世牧師
【メシアはダビデの子】
11章でイエスがエルサレムに入られてから、様々な出来事がありました。そして、12章に入ってからは、イエスの敵対者たちが、どうにかしてイエスを陥れようと、悪意のある質問をイエスに投げかけました。
それらの質問に対してイエスは適切に答え12章34節にあるように「もはや、あえて質問する者はなかった」のです。
誰もイエスに質問することができなくなり、今度はイエスの方から、律法学者たちに対して、その問題点を指摘するような話をされました。 それは35節にあるように「どうして律法学者たちは、『メシアはダビデの子だ』というのか」というものでした。
律法学者に限らず当時の人々も「メシアはダビデの子」だと思っていました。それに対してイエスは詩編110編1節を引用して、ダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのかと語り、律法学者たちの誤解を正そうとしているのです。
実際、ここでダビデが語ることには矛盾があります。しかし、イエスが語るように、ダビデは聖霊を受けて語っているということなので、ダビデ自身も理解できない神の救いの計画が語られたということなのです。
そして、そもそもの話として、イエスの弟子たちや群衆も同じなのですが、律法学者たちのメシア理解と神がこの世に送ろうとしているメシアには大きな違いがあるということです。それは、力によってローマの支配から解放するメシアではなく、愛によって真の平和を実現する、神の小羊としてのメシアなのです。
続けてイエスは38節で「律法学者に気をつけなさい」と語り始めます。
【権威者】
私たちが社会の中で生活していく時、なければ良いのにと思いながらも、なくすことの出来ないもの、必要悪と言われるようなものがたくさんあります。
また、同じ人であっても、立場が変わることによって、必要ないと思っていたものが必要になったり、反対に必要だと思っていたものが必要なくなったりするわけです。
律法学者の働きそのものは必要なものだったと思いますが、彼らに与えられたもう一つのもの、それは「権威」というもので、今の私からするならば、必要悪だと思えるのです。
私は個人的に小さな頃から権威というものが大嫌いでした。たぶん父親が非常に権威的な人間だったからだと思います。父の権威の元に家族は、ただ従うということが小学校くらいまで続いていました。
このような体験から、私は権威という言葉を、威圧的なものとして捉えてしまいますが、聖書の中でイエスに対して用いられる場合は、威圧的なことではなく、福音的な豊かな広がりを持つ言葉となっていくのではないかと思っています。
つまり、威圧して、従わせる力ではなく、信頼と尊敬の気持ちから、従いたくなるように、仕向ける力だと、私は理解しているのです。
当時のユダヤではエルサレム神殿に最高の権威があり、そこに仕える祭司、律法学者、長老たちが宗教的にも政治的にもあらゆる権威を握っていました。彼らの権威というのは、民衆を威圧して自分たちに従わせる力、暴力だったのです。
人がそのような暴力的な権威を握る時、そこには不公平や差別がはびこり、弱い者が常に犠牲となります。これについては歴史を見れば、一目瞭然で、ここで敢えて説明する必要がないほどだと思っています。
律法学者たちに代表される指導者たちは特別な服を着、挨拶されることを好み、人目につくところで、いかにも敬虔そうな振る舞いや祈りをすることによって、宗教的な権威付けをして、自分たちの立場を守っていたのです。
【権威の象徴】
また、エルサレム神殿は、その荘厳さゆえに権威の象徴でした。祖国を追われ、世界中に散らばっていたユダヤ人にとって、エルサレム神殿に参拝することは喜びだったと思いますが、同時にそれは義務であり、細かい規定に縛られたものでもありました。しかし、その宗教的基盤となるのは律法です。
律法という言葉を聞くと、私たちはすぐに律法主義と混同してしまいます。しかし、モーセの十戒によると
「わたしは主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である」(申命記5:6)という言葉で始まっています。
つまり、律法が与えられた背景には、エジプトの地で奴隷生活を送っていたユダヤ民族を神が解放してくれたという現実があるのです。その解放された民に与えられた祝福の一つが律法なのです。
本来、律法というものは人間を罪から解放するものでした。神ではないものを、間違って神にしてはいけませんよ、というのが第一戒で、偶像を拝むなというのは、ここにしか神はいないとか、これが神です、という限定を取り除いているのです。
みだりに唱えてはいけないというのも、神の名の下に戦争しろとか、誰かを殺せとか、道徳的に悪とされることを、神の名を用いて可能にしてはいけないということです。
安息日規定も、毎日、働きづめではいけないよ。週に一度は休憩しなさいということです。この後に続く、殺すな、盗むなということも同じです。殺したくなるような関係、盗みたくなるような関係から抜け出る方法があるよ。と言っているのです。
こんなことを言うと、それは富田の勝手な解釈じゃないかと反論されるかも知れませんが、私はイエスの語った福音というフィルターを通すならば、こういう解釈になると思うのです。
にもかかわらず、ユダヤの指導者たちは民衆を律法の奴隷にしてしまったのです。つまりそこには「愛」が欠けているのです。正しさとか、忠実さということだけ見れば、律法学者たちの言い分に間違いはありません。しかし、それらは神の御心ではなかったのです。
【神に愛され、神を愛する人】
さらに次の41節からを読むと、そこにはレプトン銅貨二枚を捧げた貧しいやもめの話が出てきます。
イエスは賽銭箱に向かって座り、大勢の金持ちがたくさんのお金を賽銭箱に入れるのを見ていました。どんな気持ちで見ていたのか想像してほしいと思うのです。
神殿にいた金持ちたちは、この世的には成功者、祝福された人々と映り、貧しいやもめは敗北者、祝福から漏れてしまった人かも知れません。しかし、そのような考え方は利益を追求する、経済至上主義という考え方の奴隷になっているからなのです。
現代の日本をはじめとして、一部の先進国と言われる国は新自由主義という考え方の奴隷になっているように思えてなりません。もちろん新自由主義とは何なのかと問われると、明確に答えることができないくらい、複雑な概念だと思いますが、少なくとも今の政府が進めている新自由主義は目先の利益優先にしか見えません。
経済至上主義という基本的な姿勢の上に立って、福祉や公共サービスが縮小され、公営事業が次々と民営化され、グローバル化という名のもとに様々な規制が緩和され、低賃金で雇える外国人労働が合法化されています。CMのセリフではありませんが「そこに愛はあるんか」と言いたくなってしまいます。
この考え方の奴隷でいる限り、貧しい女の人は神に愛されていることを実感することは出来ません。しかし、彼女はそんな考え方から解放され、神に愛された者として、神の前に感謝を表しているのです。
イエスは「この人は、乏しい中から自分の持っている物をすべて、生活費を全部入れたからである」と語りました。ここに愛されている者の姿、力強い姿を見ることが出来るのです。
聖書において神はどんな人であっても、私たちを愛しておられると約束してくださいます。この約束は、たとえ天地が滅びたとしても、いつまでも残る約束であり、必ずその通りになる約束なのです。
讃 美 新生470 この世の楽しみ 献 金 頌 栄 新生673 救い主 み子と 祝 祷 後 奏