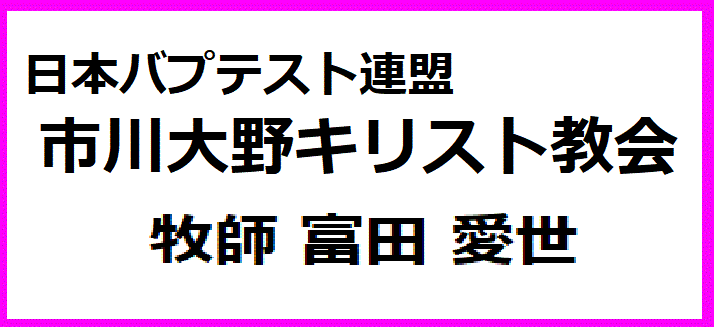前 奏 招 詞 詩編96編1~2節 讃 美 新生 20 天地治める主をほめよ 開会の祈り 讃 美 新生344 聖なるみ霊よ 主の祈り 讃 美 新生495 主よ み手もて 聖 書 ローマの信徒への手紙7章7~13節 (新共同訳聖書 新約P282)
「律法の本質」 ローマの信徒への手紙7章7~13節
宣教者:富田愛世牧師
【わたしは…】
ローマの信徒への手紙6章から7章6節までで、パウロは「人間の救いは、まず罪と律法から解放されなければ実現しない」と語りました。繰り返しになりますが、「罪と律法」と語られますが、罪イコール律法ということではありません。
律法は神が与えてくださった恵みの戒めですから、罪ではありません。しかし、人間が律法を解釈したり、用いたりする時の解釈や用い方によって罪になることがあるということなのです。
前回の7章5節に「わたしたちが肉に従って生きている間は、罪へ誘う欲情が律法によって五体の中に働き、死に至る実を結んでいました」とあります。律法を通して働く罪に支配された人間の姿がここには描かれています。
パウロは、そのような人間の姿を思いながら、この7節で「律法は罪であろうか」と自問自答しているのです
また、6節までは「わたしたち」と言っていたのが、7節の中ほどを見ると「律法によらなければ、わたしは罪を知らなかったでしょう」というように一人称単数の「わたし」という言葉を用いるように変わっています。
「わたしたち」と一人称複数で語られる時は、個人を特定するのではなく、一般化する時に用いられ、一人称単数で語られる時は、個人を特定します。したがって、ここでは人間一般についての事柄から、パウロ個人の事柄に変わったと考えても間違いではないと思います。
しかし、ここでは、わたしと語っていますが、これは個人を指しているのではなく、読者への注意喚起のために、あえて「わたし」という言葉を用いているのです。そして、この手紙を読む、ひとり一人が自分のこととして罪と向き合うことを期待しているのです。
【律法は罪か?】
さて、もう一度「律法は罪であろうか。決してそうではない」という自問自答の言葉に戻って考えていきたいと思います。
「律法は罪であろうか」という問いに対して、すぐにハッキリと「決してそうではない」と答えています。しかし、そうではないと否定していますが、律法と罪との間には関係はあるのです。
それは、律法によらなければ人間は罪を知ることがなかったからなのです。パウロはここで「むさぼり」ということを例に出して話を進めようとしています。
「むさぼり」とはどのような罪なのでしょうか。別の訳では「欲情」と訳されることもあるようです。これは他の人の所有物のように、本来、欲しがってはいけないものに向けられる欲望のことを指しています。
十戒の第十番目が「あなたは隣人の家をむさぼってはならない」とあります。バプテスト連盟の平和的信仰宣言では「主イエスによって解放された私たちは、むさぼることができない。一切を独占しようとする私たちのむさぼりが、隣人を傷つけ、世界を破壊し、戦争を引き起こしている。死者さえもむさぼられ戦争の道具とされる。むさぼりのあるところに平和はない。私たちはむさぼらない」と宣言しています。
むさぼりとは、外的物質的なことだけでなく、内的精神的なものをも含む、あらゆる罪の始まりとして捉えられているのです。
8節に「ところが、罪は掟によって機会を得、あらゆる種類のむさぼりをわたしの内に起こしました」とあります。ここに書かれている「掟」という言葉は、シナイ契約の条項として与えられた十戒を中心とする諸規定のことだと考えられています。
十戒を通して「むさぼるな」と言われると今まで忘れていた、あらゆる種類の「むさぼり」という意識が起こってきてむさぼるようになると言うのです。思い出したように罪を犯してしまう。なぜと言われても、きっと理由は見つからないでしょう。そして、これが罪の本性なのです。
続けて「律法がなければ罪は死んでいるのです」とあります。律法は何が許されない行為なのかを示しているのです。しかし、罪を犯さないように止める力は持っていないのです。かえって、禁止行為を示すことによって「むさぼり」や「欲情」を刺激して、誘惑することになるのです。
【かつて】
9節では「わたしは、かつては律法とかかわりなく生きてきました」と語ります。この「わたし」とは先ほど説明したように、パウロ個人を指しているのではなく、人間一般を指しています。
そして、この「かつて」という言葉には、まだ何も分からない乳児の頃という説とアダムの時代を指すという説があります。
昔から事件や事故で幼い子どもが犠牲になると「罪もない子どもが犠牲に」などというコメントが流れます。何歳くらいから罪の意識が明確になるのかは個人差があるでしょうが、罪の自覚、罪意識がない、気付かない年齢というものがあります。
そのような時は律法とかかわりなく生きていたということなのかもしれません。
また、アダムの時代を指すという説については、そのものズバリという感じで、天地創造の業の6日目に「人」が神に似たものとして創造されました。エデンの園では、人は神と自由に語り合い、罪という概念さえ知らずに暮らしていたということです。
いずれにしても、まだ律法が必要ではない時があったというのです。そして、その時には「罪」という概念もなく、罪が死んだような状態にあったということです。そのような時が人間にはあったのです。
しかし、それらは今も続いているのではありません。「かつて」のことなのです。そして、掟の登場によって罪が生き返って、人は死ぬべき存在となったのです。
命をもたらすはずだった掟が、律法が罪に定めるものとなってしまったということなのです。
【罪の欺き】
11節を見ると罪は「わたしを欺き」とあります。人が罪によって欺かれ、罪を犯すようになった最初の事件は創世記3章に記録されています。
創世記2章16節で最初の人アダムとエバに対して神は「園のすべての木から取って食べなさい」と語りました。しかし、3章1節で蛇は「園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか」とエバに尋ねているのです。
明らかに神の言葉とは違う質問をしているのです。しかし、似た言葉だと言われれば、似た言葉だと思います。蛇に例えられている罪は巧みな言葉で人を欺こうとするのです。
さらに蛇はエバに向かって「それを食べると神のようになれる」と欺き、神との約束を破らせました。神ではない者、つまり自分が神にとって代われるとそそのかされたのです。これが罪の本質なのです。魅力的な言葉、甘い言葉によって、人間を誘惑し、神から遠ざけ、さらに神にとって代わろうとさせるのです。
自分が神なのだから何をやっても構わないと思うことによって、あらゆる罪が生まれるのです。
13節では「善いものがわたしにとって死をもたらすものとなったのだろうか」と語りますが、すぐに「決してそうではない」と7節と同じような自問自答が繰り返されます。
本来、人間を生かすために神から与えられた律法や掟が、罪の欺きによって、正反対の働きをするようになったのです。12節にあるように律法も掟も聖であり、正しく、善いものだったのです。善いものが人間を殺すようになったのではなく、人間と律法や掟の間に罪が入り込み、律法や掟を利用して人間を殺すのです。
13節の最後のところに「このようにして、罪は限りなく邪悪なものであることが、掟を通して示されたのでした」とあります。罪という邪悪なものは律法や掟を利用するのです。そして、今の時代も聖書の言葉を利用して、私たちに働きかけるのだということを心に留めておかなければなりません。
讃 美 新生543 千歳の岩よ 献 金 頌 栄 新生669 みさかえあれ(B) 祝 祷 後 奏