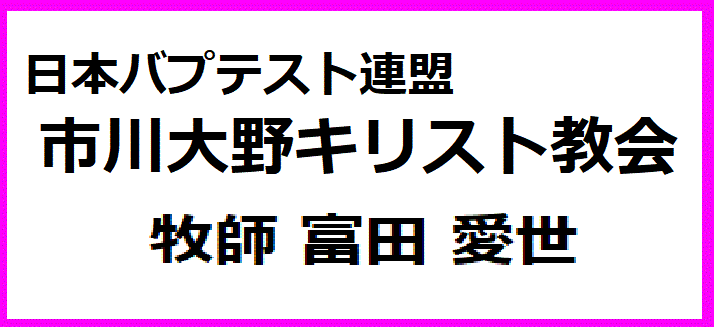前 奏 招 詞 ダニエル書2章21節 讃 美 新生 3 あがめまつれ うるわしき主 開会の祈り 讃 美 新生464 主が来られて呼んでおられる 主の祈り 讃 美 新生 71 年の始めは 聖 書 ローマの信徒への手紙13章1~7節 (新共同訳聖書 新約P292) 宣 教 「権威ある者の資質」 宣教者:富田愛世牧師 【市民道徳】 あけましておめでとうございます。今年は1月1日元日が日曜日になっているので、元旦礼拝を特別に行わずに、主日礼拝として元旦礼拝が出来ます。日程的には1週間の内に元旦礼拝と主日礼拝という形で礼拝を2回しないで済むので、楽なのかもしれません。このように日曜日と元日が重なるのは数年に一度しかありませんが、何となくケジメがつかないような気もしています。 いずれにしても1年の初めの日に礼拝を捧げられるという事は感謝な出来事だと思います。一般的には「初詣」をする日ですから、多くの教会では「初詣の代わりに、教会の元旦礼拝にお出で下さい」と宣伝しています。しかし、初詣とキリスト教の礼拝では根本的に違うところがあります。 初詣は神社仏閣にお参りして、何事もなく1年を過ごせたことに感謝し、今年1年の無事をお願いするという事が中心になります。しかし、キリスト教の礼拝は、そこに参加して、何かをお願いするわけではありません。神に対する賛美を捧げ、祈り、感謝する行為です。 ですから、教会に来て、神さまに何かお願いをするのはチョットと言われる方が時々います。厳密にはそのような意見はもっともなのかもしれません。しかし、イエスならどうなのかなと考えると、お願いでも、何でもいいよ、とおっしゃるような気がします。 もちろん、イエスは何でもありだというのではありません。ただ、そこにいる一人に目を注ぎ、その人が何を望んでいるのか、どんな状況なのか、そういったことに関心を持ち、その人に対して最善の道を、一緒に探してくれるのではないかと思うのです。 そんなことを考えながら、今日のメッセージの準備をしていました。今日の聖書箇所は、元日だから特別というのではなく、クリスマスシーズンの前まで、続けて読んでいたローマの信徒への手紙に戻ります。 先ほど司会者に読んでいただきましたが、13章1節から7節は一般的な市民道徳について語られているわけです。先ほど、初詣のような感覚で元旦礼拝に来てもイエスは受け入れてくれるのではないかと言いましたが、パウロならどうでしょうか。この箇所を読むとパウロにはイエスのようなセンスはないように感じます。 【上に立つ権威】 1節を見ると「人は皆、上に立つ権威に従うべきです」と書かれています。キリスト教に限らず、宗教は嫌いだという人の中に、宗教は厳しい掟や規則があって嫌いだという方がいます。そういう人は、ここに書かれているような「べきです」という言葉に反応してしまうのだろうと思います。 私も「べきだ」と言われると反抗したくなる性質なので、この箇所からは語りたくないな、飛ばしてしまおうかなどとも考えてしまいました。特に「上に立つ権威」などと言われると、わけもなく反抗したくなってしまいます。 パウロはなぜ、こんなことを書いているのでしょうか。そこには「神に由来しない権威はない」という確信があったようです。ユダヤ教の背景を持ち、ヘブル語聖書を信仰の規範としていたパウロにとって、神は唯一の存在であり、すべての支配者でありました。また、イスラエルの伝統において、王などの指導者は祭司や預言者によって油を注がれることによって、神からの委託を受けた者とみなされていました。 ユダヤだけではなく、異邦人の世界を含めて、世界全体を神が支配しているのですから、そこにあるすべての権威も神の支配の中にあるというのがパウロの確信だったようです。この箇所においては、ローマ帝国の皇帝すら、神の許しなしには、その権力を行使することが出来ないとパウロは考えていたようです。 ただし、神からの委託を越えて、キリスト教徒を迫害するようになった時には、上に立つ権威に対して「獣」という言葉を用いています。コリントの信徒への手紙一15章32節やヨハネの黙示録などで「野獣」や「獣」という表現が使われています。 権力が神からの委託に従って正当に用いられているのなら、その権力に逆らうことは、神に逆らうことに繋がると語るのです。そして、3節では、神からの権力を正当に行使している権力者は正しい裁きを行うというのです。ですから、善を行う者は権力者を恐れることはないが、悪を行う者は権力者を恐れるのだ、だから善を行うように努めなさいと勧めているのです。 【良心に従う】 5節には「良心のためにも、これに従うべきです」とあります。権力者に従うという事と、道徳的に正しい行いをすることが、同列で語られていますが、ここで大切なことは、正しい行いの動機という事ではないでしょうか。 私たちが行うべき道徳的な正しさとは、それぞれの「良心」に従ったものであることが大切なのです。 ここに書かれているように、悪を行った時に裁かれるという恐怖心から、悪を行わないようになるという、いわゆる抑止力的な裁きのあり方ではなく、善を行うことによって得られる「良心」の安らぎという事の大切さが語られていると思うのです。 今、私たちの周りには、武力に対しての抑止力から犯罪に対する抑止力まで、様々な抑止力というものがあります。未熟な社会にとっては抑止力が必要なものなのかもしれませんが、抑止力に頼っているうちは成熟した社会にはなれないのではないでしょうか。 抑止力を必要としないで、それぞれの良心に従うことによって、道徳的な正しさを身に着けることのできるような社会が、一つの理想なのかもしれません。そして、パウロはそのような社会を前提に語っているように思えます。 次の6節には、権威者は神に仕える者で、そのために励んでいるのだから、貢を納めることは理に適っていると語るのです。そして、7節では義務を果たすという事について語り「貢を納めるべき人には貢を納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい」と締めくくっています。 この箇所の前にあたる12章9節からの箇所では「愛には偽りがあってはなりません」と語り、この箇所の次に当たる13章8節からは「隣人愛」について語っています。その間に、このような道徳的なことが語られているのは、なぜなのでしょうか。 【神によって立てられたもの】 本当の意図は、この手紙を書いたパウロにしか分からないのかもしれません。ですから私たちは、この手紙が書かれた時代背景や前後に書かれていることから、想像するしかありません。 時代背景としては、ローマ帝国の属州となって、様々な抑圧、搾取を受けていた時代です。そして、直前の12章に書かれていたことは、慎み深い信仰をもって、旅人をもてなし、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣き、「できれば」平和に過ごし、復習してはいけない。ということが語られていたのです。 パウロは、これらの事をローマに住んでいるクリスチャンに向けて、ローマに立てられた教会に向けて語ったのです。しかし、それは命令するような形で語ったのではないと思うのです。なぜなら、ローマの教会の人々と面識があったわけではありませんし、パウロがローマの教会を指導する立場にあったわけでもないのです。 普通に手紙として「こうであったらいいよね」という程度の重みで書いたのではないかと思うのです。そして、後半に「貢」や「税」のことが書かれていました。当時のユダヤ社会で徴税人は人々から嫌われていました。ローマ帝国の手先として税金を徴収していると思われていました。 そんな徴税人に対して、イエスはどんな態度をとっていたでしょう。他のユダヤ人から排除され、無視されていた徴税人に声をかけ、彼らと一緒に食事をしました。考えてみれば、税金に苦しんでいるけれど、それは徴税人が悪いわけではありません。彼らにも生活があり、生きていくためには、何か仕事をしなければならなかったのです。それが、たまたま徴税という仕事だったとしたら、徴税人が悪いわけではないのです。 ローマ帝国が神によって立てられた権威なのか、どうかは歴史が証明しています。しかし、その時代を生きていた人々にとっては「わからない」ことではないでしょうか。 今、これを読んでいる私たちは歴史から学び、神によって立てられる権威とは、どのようなものなのかを、ある程度、判断することが出来るのかもしれません。ただ、私たちは神ではありませんから、裁くことはできません。神から与えられている「良心」に従って、そして、愛を持って権威と呼ばれるものを見張っていく必要もあるのです。 祈 り 讃 美 新生 91 恵みのひかりは 主の晩餐 献 金 頌 栄 新生673 救い主み子と 祝 祷 後 奏
2023年1月1日 主日礼拝
投稿日 : 2023年1月1日 |
カテゴリー : 礼拝メッセージ -説教ー