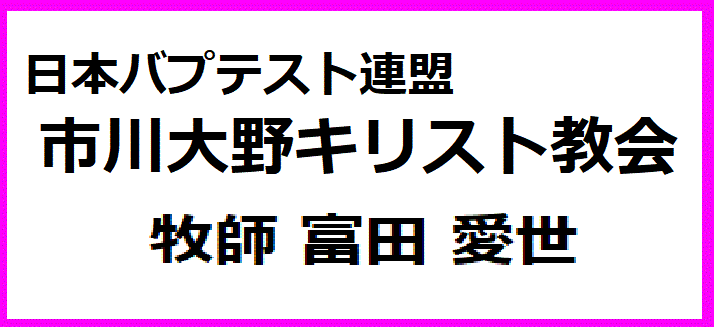前 奏 招 詞 詩篇103編14節 讃 美 新生120 主をたたえよ 力みつる主を 開会の祈り 讃 美 新生140 空の鳥を見よと 主の祈り 讃 美 新生426 語りませ主よ 聖 書 ローマの信徒への手紙1章16~17節 (新共同訳聖書 新約P273)
「福音を恥としない」 ローマの信徒への手紙1章16~17節
宣教者:富田愛世牧師
【福音は恥?】
ローマの信徒への手紙は18節から本題に入るわけですが、その前に丁寧な自己紹介と挨拶があり16~17節で主題の要約をしています。
そこには、何とかして一人でも多くの人に、これから伝えようとする福音を理解してほしい、誤解しないでほしい、という強い思いが込められているのです。
この要約は「わたしは福音を恥としない」という言葉から始まっています。何となく、消極的な言葉に聞こえると思いませんか。もっとはっきり「わたしは福音を誇る」と言えばいいのにと私は思っていました。しかし、当時の状況を考える時パウロのこの言葉は決して消極的な意味ではなく、説得力のある言葉だったのだということに気づかされます。
恥としないと言うからには、恥としている人もいたということです。パウロ自身も以前は恥としていました。だからこの福音を信じる者たちを迫害しました。しかし、今は「恥としない」と言い切っています。
それでは福音を恥としていたのは誰でしょうか。パウロ3種類の人々を思い描いていました。第一はユダヤ人です。ユダヤ人にとってイエスは大工の息子に生まれた「ただの人」で、最後には犯罪者と一緒に十字架で処刑されました。こんな男が救い主、メシヤであるということはユダヤ人にとって、つまずきとなりました。
第二はギリシャ人です。ギリシャ人は教養を重んじ、文化を誇りました。福音の中にはプラトンやアリストテレスといった偉人たちの知恵のかけらも見いだせないと彼らは理解していました。学問、教養のある者にとって、イエスの生きざまなど不合理なことで、それを信じるなど愚かで恥ずかしいことでした。
第三はローマ人です。ローマ人にとって福音は、敗戦国、弱小民族の宗教でした。信じるならローマの神々を信じたほうが得になると思っていたでしょう。この世的な力も権力もない神を信じるなど、やはり愚かで恥ずかしいことでした。
これらの思いを私たちは第三者として聞くことはできません。私たちは「福音を恥」と思ったことがないでしょうか。私はあります。人前で「私はクリスチャンです」とはっきり告白できなかったことが、数えきれないくらいありましたし、今も同じです。どうして恥ずかしく思うのだろうかと考えると、やっぱり3つの大きな理由があると思います。
第一は、私がクリスチャンらしくないから、恥ずかしくて言えないのです。クリスチャンらしくないとはどういうことか。勝手なクリスチャンのイメージを作り、それに当てはまるかどうかで判断する。つまりはユダヤ人的な思いがあります。
第二は、非科学的な感じがするのです。聖書に書いてある奇跡や復活はどう考えても科学的に解明できないことで、非科学的です。教養のある人間がそんなことを信じるなんて恥ずかしいというギリシャ人的な思いです。
第三は、日本ではクリスチャンは人口の1パーセントにも満たない、弱小集団、マイノリティーです。力や権力を持った人と知り合う可能性もなく、何の得にもならないし、変な目で見られそうだと思う、ローマ人的な思いがあるのです。
【福音は力】
この世の価値観でみるなら、福音には恥ずかしく思ってしまう要素がたくさんあるのに、なぜパウロは「恥としない」と言い切るのでしょうか。それは「信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです」ということなのです。
福音は神の力なのです。ギリシャ語で力を意味する言葉はデュナミスとエネルガイアと言う2つの言葉があります。デュナミスと言う言葉はダイナマイトの語源であり、力そのものを表しています。エネルガイアはエネルギーの語源で、力の作用、働きを意味しています。
ここでパウロはデュナミスという言葉を用いて「神の力」を説明しています。デュナミスと言うと分かりにくいので、これを語源としたダイナマイトを例に出して考えると少し分かりやすいように思います。
このダイナマイトは炭坑などで石炭や鉱石を採掘する時に邪魔な岩などを破壊することを目的として作られました。価値のない岩を破壊し、その先にある価値のある石炭や鉱石を手に入れるのです。
福音とは力そのもの、デュナミス、ダイナマイトです。人が福音を受け入れると、それはその人の内側で爆発し、罪と汚れを破壊します。そして、その先にある神の赦しと救いを手に入れることができるのです。
福音を受け入れるという事は、何かが壊されるという事なのです。その何かとは、今まで罪の中にいた自分なのです。自分が壊されるということを考えたことがありますか。教会の中ではよく、砕かれるとか砕かれた魂と言います。
パウロにとってこの「壊される」というできごとはダマスコへ行く途中の道で起こりました。今まで、自分の目で見たいものを見、自分の足で行きたい所に行けたのです。しかし、突然の光によって目が見えなくなってしまいました。自分の目で見ることができなくなり、行きたい所に行くには、人の手を借りなければ行けなくなりました。つまり、今までは自分ひとりで何でもできる、他の人の手伝いはいらない。もっとはっきり言うなら、自分が神であって、他に自分を救ってくれる神など必要ないと思っていたのです。
パウロは目的地であるダマスコに行くため、人の手を借りました。彼にとって一番したくなかったことです。屈辱的なことでした。ダマスコについて、パウロはアナニヤという人の家に行きました。アナニヤはパウロがこの世でいちばん嫌っていたクリスチャンでした。そして、この世でいちばん嫌っていたクリスチャンであるアナニヤによって、もう一度目が見えるようになりました。自分の目なのに、自分で見えるように治すことができず、他人の力によって見えるようになったのです。
この出来事はパウロにとって簡単な出来事ではありませんでした。死ぬほど恥ずかしい思いをしたに違いありません。そして、この後の出来事もパウロにとって恥の上塗りでした。福音の力とは何かが上手くいくようになるということではありません。自分自身が内側から変革されていく、神の計画にそった者に変えられていくということです。
それでは、福音は誰に対して「救いをもたらす神の力」となるのでしょうか。それは「ユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも、信じる者すべて」なのです。何の区別も差別もなく「信じる者すべて」に対する神の力なのです。
信仰とは救われるための条件ではありません。「信仰がなければ救われない」という言い方は間違いです。もし条件であるなら、神の恵みによる救いではなくなり、福音を律法化することになってしまいます。ニグレンというスウェーデンの神学者は「信仰は救いの条件ではない。福音が働いた時の人間の状態である」と語っています。
「信仰」という言葉を私たちは、あまりにも軽々しく使い過ぎるような気がします。ある時にはこの言葉が錦の御旗のようにふりかざされ、自分を正当化し、他人を裁く道具になったり、また、大義名分として無理を通すために用いられたりします。それはもう信仰ではなく、自分勝手な信心でしかありません。信仰は一方的に恵みとして与えられる、神の賜物なのです。
【神の義】
17節からは義について語られます。「福音には、神の義が啓示されていますが、それは、初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです」と書かれています。
神の義は福音の中に啓示され、信仰を通して実現されるとパウロは語ります。ユダヤ人は神の義を律法の中に見いだそうとし、必死になって律法を守り、行ないました。パウロもそうでした。確かに神の本質は義なのですから、律法の中にあります。
しかし、それだけが神の義だったとするならば、それは、人を殺す義となります。なぜなら、誰ひとり律法を守りきることのできる人はいないからです。
神の義にはもう一つの面があります。それは「罪人を義とする義である」とパウロは語ります。これが福音なのです。そして、この義は信仰においてはじまり、信仰に行き着くのです。
宗教改革者のマルチン・ルターは、初め神の義を「義人に報いを与え、罪人を罰するところの義」と理解していました。それゆえに、いつも脅え、本当の平安を経験したことがなかったそうです。ところが、ある時このローマの信徒への手紙1章17節に触れ、神の義は「罪人を義とする義」であると示され、魂に平安を得、宗教改革という大きな働きをなし遂げる原動力となったと言われています。
この福音はその人の内に入り爆発した時、パウロを変え、ルターを変え、教会を変えていったのです。
【信仰による義人】
最後に「正しい者は信仰によって生きる」とあります。これは旧約聖書ハバクク書2章4節の言葉を引用したものです。この旧約聖書の言葉はユダ王国がアッシリヤに攻められ、バビロンによって滅ぼされた頃のもので「神を無視する傲慢な者は亡び、神を信じて立つ正しい者は生かされる」ということを語っています。
この信仰は、救いの条件でもなく、義に至る道でもありません。神に敵対する者にとっては、恥であり、価値のないもの、そして、その力によって自分が砕かれ、弱さを思い知らされます。
この弱さを知ることが、信仰なのです。信仰によって生きるとは、この弱さを知らされないかぎり、神の前にへりくだれない罪人を神が義としてくださり、生かしてくださると言うことなのです。
讃 美 新生380 罪の世に過ごす 献 金 頌 栄 新生674 父 み子 聖霊の 祝 祷 後 奏