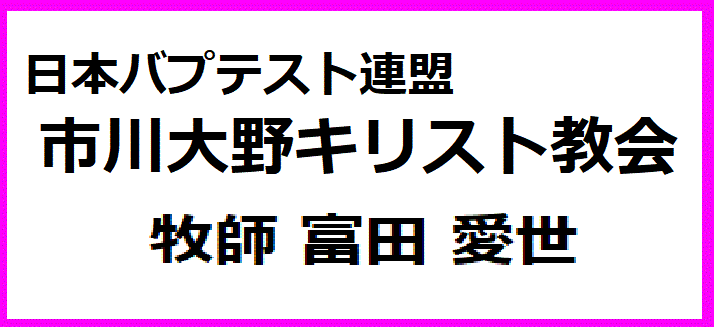前 奏 招 詞 レビ記18章5節 讃 美 新生120 主をたたえよ 力みつる主を 開会の祈り 讃 美 新生367 神によりて 主の祈り 讃 美 新生497 イエスさまは心のともだち 聖 書 ローマの信徒への手紙10章5~13節 (新共同訳聖書 新約P288) 宣 教 「信仰の言葉」 宣教者:富田愛世牧師 【律法による義】 パウロは10章5節で「モーセは、律法による義について」という言葉で書き始めています。キリストに出会う前のパウロにとって、そしてイスラエルの民にとってモーセとその律法は、救いのために必要不可欠なものでした。創世記から申命記までは、モーセ五書、トーラーと呼ばれ、特別な位置を占めていました。 モーセがいなければ律法が与えられなかったし、律法がなければ何をして神から義と認められるのか分からなかったからです。このように言うと、今の私たちクリスチャンにとっては「そうかな」と思ってしまうでしょうが、当時のユダヤ人には、これが常識でした。 次に出てくる「掟を守る人は掟によって生きる」という言葉は、レビ記18章5節の言葉で、そこには「わたしの掟と法とを守りなさい。これらを行う人はそれによって命を得ることができる。わたしは主である」と書かれています。 文字として残されている律法と、父祖からの言い伝えとしての律法は、ユダヤ人にとって何にも代えられないくらい大切なもので、それを行うことは、生涯を通して続けていかなければならないものでした。 しかし、現実に目を向ける時、それらを守ることの難しさ、という壁にぶち当たることも事実だったのではないでしょうか。 そのような律法による義に対して、信仰による義とは次のようなことだと言って、6節から8節にかけて語り始めています。ここに書かれている言葉は申命記30章12~14節までに書かれている言葉を引用しています。少し長いですが読ませていただきます。 「12それは天にあるものではないから、「だれかが天に昇り、わたしたちのためにそれを取って来て聞かせてくれれば、それを行うことができるのだが」と言うには及ばない。13海のかなたにあるものでもないから、「だれかが海のかなたに渡り、わたしたちのためにそれを取って来て聞かせてくれれば、それを行うことができるのだが」と言うには及ばない。14御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。」 【言ってはならない】 まず6節は「心の中で『誰が天に上るか』と言ってはならない」とあります。この言葉は申命記30章12節の言葉から語られています。ところが、次の7節では「だれが海のかなたに渡り」という言葉ではなく、「誰が底なしの淵に降るか」という言葉が出てきます。 パウロはヘブル語聖書を正確に引用していないのでしょうか。これは前回のところでもお話したように、パウロの解釈が入った引用の仕方がされているからだと思われます。 詩編107編26節に「彼らは天に上り、深淵に下り 苦難に魂は溶け」という言葉があり、「つまずきの石、妨げの岩」と同じように「海」と「深淵」をつなげて語っているようです。 申命記で「天」と「海」が対称的に語られていたのと同じように、詩編では「天」と「深淵」が対称的に語られているので、その二つを合わせて、より意味深くなるように両方を合わせて語っているのです。 そして、なぜ「誰が天に上るか」と言ってはいけないのかというと、すでにキリストが復活して天に上ったのだから、もう誰も天に上る必要はないというのです。また、人間が高慢な思いで「天に上る」と言うとすれば、それはキリストが必要ないと言っているのと同じだというのです。 次の「だれが底なしの淵に下るか」と言ってはいけないのは、当時の人々の信仰として、キリストが十字架で死んだ後「陰府」に下ったと信じられていたからです。この「陰府」に下ったキリストを神は死人の中から引き上げてくださり、それによって死に勝利したと考えられていたのです。 同じことが人間にできるわけがなく、人間には許されていない行為なのです。もし誰かが、高ぶった思いをもって「底なしの淵」「陰府」に下ろうなどと思ったとするなら、それは、神を冒涜する行為となるのです。 そして、キリストの死を否定することになり、キリストが死ななかったのならば、復活もあり得ませんし、死への勝利、救いの完成という事も意味のないお話になってしまうのです。 【御言葉はあなたの近くに】 次に8節で「信仰による義」の本質について語り始めます。パウロが宣べ伝えている信仰の言葉とは、私たちが修行を積んだり、そこにたどり着くまで、長い道のりを歩き続けたりするようなものではありません。 「あなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある」というのです。 これは生まれながらのユダヤ人として、熱心に律法を行い、守り続けてきたパウロだからこその発言ではないでしょうか。長い年月、自分い鞭打って、厳しい修行を続けていたのです。そして、遥か彼方にある「救い」というものを見上げ続けていたけれど、見つけることができなかったのではないでしょうか。 9節では「口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら」救われると語ります。同じ内容のことが10節でも繰り返され「実に、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです」とあります。 「口で告白する」ことと「心で信じる」ことが組になっています。どちらか一つではいけないようなのです。 口先だけで「信じる」と言ったとしても、それは救いにはつながらないのです。反対に「心で信じている」と思っていても、その人の口から出てくる言葉に「愛」や「憐れみ」がなかったとするならば、それは本当に信じていることにはならないという事ではないでしょうか。 また、このようにパウロが語る背景として、当時のクリスチャンたちが置かれていた社会的な状況というものも強く影響しているのではないでしょうか。 当然の事として、ユダヤ人にとっての多数派はユダヤ教でした。そして、ローマ社会にとっての多数派は、ローマ皇帝を「現人神」として崇拝する皇帝崇拝者だったと思われます。 そのような逆境の中で、迫害される危険を感じつつも、イエスが主であると、その信仰を告白し続けていたのです。 【誰も失望しない】 11節には「主を信じる者は、だれも失望することがない」と書かれています。これは前回の9章33節で引用されたイザヤ書28章16節がもう一度引用されています。イザヤ書では「信ずる者は慌てることがない」と訳されています 心で信じる者は、イザヤ書にあるように「堅く据えられた礎の、貴い隅の石」なのです。どんなことがあっても揺らぐことがなく、慌てることもないのです。パウロにとっては、それが「失望しない」ということに繋がるのです。 さらに12節にあるように、キリストによる救いの業には「ユダヤ人とギリシア人の区別」がないのです。つまり、ユダヤ人であっても、異邦人と言われる外国人であっても、すべての人が救われるという、神の壮大な計画の中に私たちは生きているという事なのです。 13節では「主の名を呼び求める者はだれでも救われるのです。」と語られます。ユダヤ人のように「主の名を呼び求めるだけでなく、割礼を受け、律法を守らなければならない」とは言っていないのです。 「主の名を呼び求める」とはどういうことでしょうか。「苦しい時の神頼み」は都合がよすぎていけないのでしょうか。もし、そうだったとするなら「主の名を呼び求める者はだれでも救われる」とは言わなかったと思います。 苦しい時だけではなく、嬉しい時も、楽しい時も、悲しい時も「主の名を呼び求める者は」という条件を付けたのではないでしょうか。 このような素晴らしい「福音」を私たちは受けているのに、隣人に対して条件を付けることがないでしょうか。教会はもう一度、問い直していかなければならないと思っています。 しっかりと聖書の言葉に立ち返り、イエスが語り、生きた、ガリラヤの地に根差した福音を再確認する必要があるのです。 讃 美 新生250 イエスは主なり 主の晩餐 献 金 頌 栄 新生674 父 み子 聖霊の 祝 祷 後 奏
2022年10月2日 主日礼拝
投稿日 : 2022年10月2日 |
カテゴリー : 礼拝メッセージ -説教ー