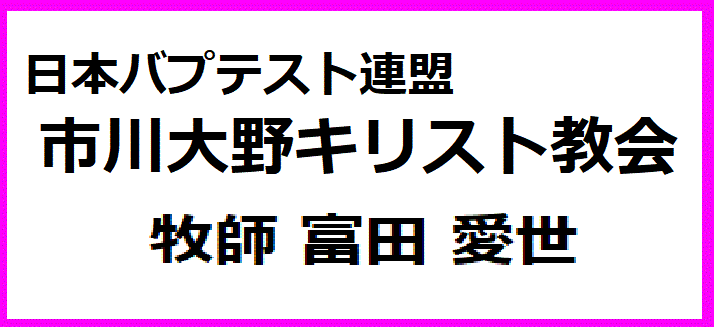前 奏 招 詞 エレミヤ書9章23節 讃 美 新生 14 心込めて 主をたたえ 開会の祈り 讃 美 新生 59 父の神よ 汝がまこと 主の祈り 讃 美 新生376 友よ聞け 主のことば 聖 書 フィリピの信徒への手紙3章1~11節 (新共同訳聖書 新約P364) 宣 教 「本当の価値」 宣教者:富田愛世牧師 【3つの警告】 今日は3章1節からになっていますが、内容的には後半の「同じことをもう一度書きますが」というところからになります。前半にある「では、私の兄弟たち、主において喜びなさい」という言葉ですが、「では」ではなく「最後に」と訳されることもある言葉で、2章の最後に結びの言葉として書かれたものだと考えられています。 この3章1節の後半で、パウロは「同じことをもう一度書きますが」と語り始めています。パウロという人は、しつこい性格だったようで、大切だと思ったことは、何度も繰り返し伝えていたようです。パウロにとって大切な事とは、フィリピの手紙ですから「喜び」という事もあったと思いますが、ここで語られることは、フィリピ教会の人たちを惑わす人々に注意しなさいという事でした。 2節でパウロは、犬に注意し、よこしまな働き手に気を付け、割礼を持つ者を警戒しなさいとフィリピ教会に警告しています。3つの警告が出されているわけですが、これは3種類の人々という事ではなくて、3種類の書き方をすることによって、事の重大さを強調しているのではないかと思うのです。 そして、ここには2つのメッセージが込められています。一つ目は教会に及んでいる危険です。フィリピ教会は危険にさらされていたという事です。その危険とは何だったのでしょうか。 それはクリスチャンたちを改宗させようとするユダヤ教徒の事だったのです。ユダヤ教徒というと、民族的にもユダヤ人の血を受け継ぐ人たちと考えるかもしれませんが、ここで語られるユダヤ教徒は異教からユダヤ教に改宗した人たちだと考えられています。だからパウロは「切り傷にすぎない割礼」という言い方をしたのではないかと思うのです。 この当時のキリスト教は、まだ、ユダヤ教の一派だと思われていました。ユダヤ教キリスト派という呼び名があったそうです。ですからユダヤ教徒の人たちがキリスト教という共同体にも簡単に入ってきて、混乱させていたようなのです。 彼らはキリストを信じることだけで救われるのではなく、プラスαの条件が必要だと主張しました。特に割礼を受けるという事は重大だったようで、生粋のユダヤ人であったパウロから見るならば、非常に滑稽なことだったようです。 【肉の誇り】 二つ目のメッセージは律法主義的な形に捉われる危険です。フィリピ教会のクリスチャンは異教徒からの改宗者が多数を占めていました。そういう人たちにとってユダヤ教というのは、キリスト教の母体となったもので、そこで行われる伝統的な儀式や律法に、特別な魅力を感じたとしても不思議ではないと思います。 現代のキリスト教会においても、ユダヤ教の伝統的な儀式や律法に魅力を感じる人が少なくはありません。それが高じて異端のグループを作ってしまう人たちもいるのです。ユダヤ教そのものを否定するつもりはありませんが、キリストの福音という、人を罪から解放させる言葉と比べるならば、伝統的な儀式や律法には何の意味もないと思うのです。 ここで、自分をユダヤ教徒だと主張する人たちにとって、なくてはならない印が割礼でした。私はイスラエルに行った事が無いので、聞いたお話しかすることが出来ませんが、以前、イスラエルに行かれた、ある先生が、年配のユダヤ人の方に「ユダヤ人のアイデンティティーは何ですか」と尋ねたそうです。するとその老人は、きっぱりと「割礼です」と答えたそうです。昔も今も変わらないようです。 しかし、パウロはそれを「切り傷にすぎない」と語り、その意味を問いかけているのです。もちろん、フィリピ教会を混乱させているユダヤ教徒は異教からの改宗者ですから、その意味を問いかけることに大きな意味がありますが、生粋のユダヤ人であったとしても、その意味を理解できる人は、そう多くはなかったのかもしれません。 ヘブライ語聖書において、割礼とは神が、神の民と認めた者に対して受けさせる「しるし」でした。そう考えるならば、受けるか受けないかに意味があるのではなく、神の存在にこそ意味があるという事は、簡単にわかるはずです。しかし、律法主義や形式主義に陥ってしまった人は、思考停止状態にあるので、それを理解することが出来なくなってしまうのです。 真の割礼は、神の霊によって与えられるものです。ですから、それを信じて、確信していれば平安が与えられるのです。しかし、肉の割礼は、形だけですから、その後ろ盾になるものを必要とします。それが律法の行いとなるのです。 毎日の祈り、律法を忠実に守ること、生贄を捧げること、伝道すること、そういった人間の努力と業績を頼みとする愚かなものとなるのです。 【塵あくた】 かつてはパウロも肉的なしるしを誇りとしていましたが、キリストとの出会いによって、その価値観が逆転しました。 5節から6節にパウロの肉的な誇りが書かれています。 「わたしは生まれて八日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非のうちどころのない者でした。」 パウロが誇りとしていたものは、手に入れようとしても、手に入れることの出来るものではありません。八日目に割礼を受けるという名誉な事柄が欲しいと言っても、もし大人になってからユダヤ教に改宗したのなら絶対に無理な事です。 イスラエルの民に属しという事も、ベニヤミン族の出身という事も生まれながらのもので、生まれてしまった人にとってはどうにもできないことです。手に入れることの出来ない貴重なものなのです。しかし、今のパウロにとっては何の価値もなくなってしまいました。 7節を見ると「しかし、わたしにとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失と見なすようになったのです」と書かれています。なんの価値もないどころか、損失だと思えるようになったというのです。 さらに8節を見ると「そればかりか、わたしの主キリスト・イエスを知ることのあまりのすばらしさに、今では他の一切を損失と見ています」と語ります。7節で回心した時のことを語り、この8節では今の心境を語っているのです。 パウロにとってキリストを知ることの素晴らしさとは、どれほどのものだったのかは、続きを見ると分かるのですが、「キリストのゆえに、私はすべてを失いましたが、それを塵あくたとみなしています」と語っています。何度も繰り返していますが、キリストを知る以前までは宝のように思っていたもの、割礼や律法の行いは、キリストの信仰の前には「損失」とさえ思えるようになってしまった。 さらに、キリストのゆえに、それらすべてを失ったが、それらは「塵あくた」だというのです。ただこの言葉も聖書を日本語に訳された先生方の品位の高さが邪魔をして、パウロの気持ちが伝わらないような気がします。パウロの思いとしては、そんなものは「くそくらえだ」と訳した方がその気持ちを表しているのです。 【信仰による義】 9節からは、パウロにとってテーマとなるような事柄が語られています。それは「義」という事です。神によって「義」と認められるかどうかという事が、究極的な問いかけであり、その答えをキリストによって得ることが出来たのです。 パウロは「律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。」と語っています。律法を行うことによって「義」と認められようとするという事は、自分の義にすぎないのだというのです。何かをして、という事は、究極的には自分のためでしかないのです。 それに対して、「キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義」という事ですから、義というものは自分の努力、力によって獲得するものではなく、神から与えられるのだという事です。そして、神から与えられる「義」というのは自分のためではないのです。他者のためなのです。 キリストへの信仰とは福音を生きることに他なりません。福音を生きるならば、隣人に気付かされてしまうのです。隣人に気付いてしまった時、そこに泣く者がいるなら共に泣き、喜ぶ者がいるなら、共に喜ぶのです。それが神に認められて義とされるということなのです。 10節では、もう一度「キリストを知る」という事について語ります。キリストを知るという事の素晴らしさとは、自分にとって都合の良いことが起こるとか、都合の良い状態が続くという事ではありません。「その苦しみにあずかって、その死の姿にあやかりながら」という事なのです。 苦しみがあるのです。死を覚悟しなければならないことも起こるのです。しかし、その先にあるものは、11節で語られる「復活」という事なのです。そして、10節の前半を見ると「キリストとその復活の力とを知り」とあります。キリストを知るという事は、その復活の力を知るという事でもあるのです。 この力という言葉は、爆発的な力を意味しており、ダイナマイトの語源となった言葉が使われているのです。それほど大きな破壊力を持つ力が、死を破壊し、人間を縛り付けている罪の力を破壊してしまうのです。パウロの人生を変え、今、私たちの人生を変えてしまうほどの力が、キリストの福音なのです。 祈 り 讃 美 新生537 重い荷をにない 献 金 頌 栄 新生674 父 み子 聖霊の 祝 祷 後 奏
2023年7月16日 主日礼拝
投稿日 : 2023年7月16日 |
カテゴリー : 礼拝メッセージ -説教ー